桝田 青花
総合政策学部 3年生(参加時)
- 派遣プログラム
- 国際ボランティア
- 派遣先機関
- カンボジア日本人材開発センター(CJCC)
- 派遣時期
- 2024年度秋学期

藤田 佳吾
国際学部 2年生(参加時)
- 派遣プログラム
- 国際ボランティア
- 派遣先機関
- ネパール バラゴンアカデミー
- 派遣時期
- 2024年度秋学期

なぜ留学しようと思ったのか?
高校生の時から開発途上国における貧困問題と世界の格差問題に興味を持ち、ずっと途上国に行ってみたいと考えていました。また中学生と高校生の時にそれぞれ短期でアメリカに行ったことがあったので、せっかくなら人と違うところに行きたいというチャレンジ精神も強くありました。もともと好奇心旺盛で、様々な興味分野に飛び込んでいくことが自分の性格です。人と関わることが大好きなこともあり、ネパールで小学校の教員として業務を行うことは、社会問題の解決と自分の興味分野がマッチしていたので、ネパールを選びました。/p>
留学を実現するまでに、どのような準備をしましたか?
ネパールで半年間生活するとなっても、始めは全く想像がつきませんでした。留学の約1年前に結果が出たこともあり、まず始めは同じ場所に渡航された先輩方に話を聞くことから始めました。同時に自分でも本を読んだりYoutubeで動画を見たりして情報を収集し、自分が行う業務の概要や行く国の生活事情に関しての解像度を上げていました。渡航前学習であるボランティアゼミでは、1週間丸々かけて課題図書を分析し、毎週ある読書会に備えていました。渡航直前は特にワクチン接種やビザの取得が必要であったため、計画的な行動を心がけていました。
留学中で、印象的な出来事
業務面で一番驚かされたのは、日本よりも学歴社会だということです。小学校からGPAを意識し、より良い成績の取れる環境を求めて転校を繰り返す生徒が多いことや、どの学校でも、生徒の成績を町に張り出していたことは衝撃でした。生活面では、日常とヒンドゥー教の密接さに驚きました。例えばお寺を通るたびにその場でお祈りをし、祝日や誕生日には宗教儀式を行い、動物を生贄として捧げるなど、従順な教徒が多かったです。また、ご飯を1日に5回食べることや、鶏を生きた状態から裁いて鶏肉を食べた経験からは、食事のありがたみを感じた。
1日もしくはプログラム全体ののスケジュールを教えてください。
ネパールの朝は毎朝7時前に始まります。朝のチヤと軽食を食べて行く準備をし、家を出る前にもう一度ご飯を食べて出発します。学校へは毎朝スクールバスで行き、2〜7時間目までの授業を担当します。放課後は、一部の生徒はスポーツやダンスの為に学校に残って練習をし、他の生徒はすぐにスクールバスで帰宅します。家は徒歩30分ほどで着く場所にあったので、ほのかに香る土っぽい香りを嗅ぎながら町で一番高いお寺に上り、夕陽を背にヒマラヤ山脈を眺めることが私の1日の楽しみでした。時間が本当にゆっくり流れていて、いい意味で時間に縛られない生活を送っていました。
留学での経験は、今後の就職・進路選択にどんな影響を与えると思いますか?
本プログラムに参加した理由の一つに、将来国際協力に携わりたいという目標があったため、途上国での実務的な業務ができたことは、将来の仕事像を具体的に想像することに繋がりました。また、途上国に1人で飛び込んでいった経験は一生の財産になるし、今後の自分の生きる上での価値軸みたいなものになると思います。留学には、世界を通して自身では気付けなかった自分を探求し、これからの行動を変えていくための動機がたくさん詰まっています。単に語学力だけではない自己成長と、就職や進路を見据えた目標の明確化に繋がると思います。
特に成長したと感じられる点
タフネス
その理由
言語も文化も全く違う中で、伝えたいことが伝わらなくて苦しい時がほとんどでした。そんな時でも伝わるまで説明を工夫したことは、タフネスの向上につながったと思います。また生活面では、日本ほどモノや設備が整っているわけではないので、限られたリソースの中で粘り強く生きるタフさも得たと思います。
これから留学する人に向けたアドバイス・メッセージを!!
世界には日本と同じ国なんて一つもありません。留学では、日本にいては絶対にできない体験から自分の価値観、人生観がガラッと変わる経験をするでしょう。「こう思ってたのに」という自分の当たり前が通用せず、価値観の違いに悩む経験が必ずあります。そんな価値観をぶっ壊される経験を重ねることで、大いに成長できると思います!
中谷 のの子
総合政策学部 3年生(参加時)
- 派遣プログラム
- 国際社会貢献活動
- 派遣先機関
- ネパールのParagon Academy
- 派遣時期
- 2024年度春学期

なぜ留学しようと思ったのか?
もともと海外に興味があり、大学在学中に留学に挑戦したいと思っていました。また、将来、国際協力関連の仕事や途上国の子どもたちの教育などに関わる仕事に就きたいと考えてきました。なので、この国際社会貢献活動の中で、現地の小学校の先生として五ヶ月間過ごせるものがあると知った時、先生として子どもたちと直接関われる・学校という教育現場で働ける・ホームステイをして現地の方と変わらない生活をすることで国を深く理解できるという点から、自分にぴったりなものだと感じ、ネパールでの活動に参加することを決めました。
留学を実現するまでに、どのような準備をしましたか?
応募までは、このプログラムのために履修が希望されている教科を履修していました。具体的には「国際情報分析」「プロジェクトマネジメント」などです。情報を正しく得て分析する力、課題を発見し分析し効果的な解決策を提案していくことなどを学びました。ネパールの小学校への派遣が決まった後は、小学校で教える内容を考えたり、授業で使えるような教材を作成したりしていました。また、ネパールの小学校では英語で教えるので必要ないですが、日常生活のコミュニケーションのためにネパール語の勉強も少しずつ始めました。
どのような留学生活でしたか?
とにかく、子どもたちの笑顔に囲まれて幸せな毎日でした。小学校に行くと「せんせい!」「今日の授業はいつ?」「今日の授業では何するの?」と子どもたちは沢山話しかけてくれ、とても楽しく、常に引っ張りだこでした(笑)。授業では自作のカードや表を使ってカタカナを一緒に学んだり、日本語の歌を歌ったり、こどもの日や七夕のイベントをしたり、けん玉を練習したり、色々なことをしました。家に帰ってからはホストファミリーにネパールの様々なことを教えてもらったり、一緒にご飯を食べたり、談笑したり、充実した時間を過ごしていました。
1日もしくはプログラム全体ののスケジュールを教えてください。
ネパールでは朝起きると、甘い紅茶とおやつの時間から始まります。そのあとご飯を食べ、朝9時半くらいにスクールバスで学校に向かいます。3コマほど授業をした後、他の先生と一緒に給食を食べ、午後も3コマほど授業をしたあと帰宅、そして甘い紅茶とおやつの時間。そのあとは自分の部屋で休憩したり次の日の準備をして、ご飯を食べて夜10時には寝ていました!学校での授業がある日はこのような感じです。また、授業の日以外に周辺の学校でけん玉の指導も行っていたのですが、その日は2校ほどで教えてから帰宅というスケジュールでした。
留学中で、印象的な出来事
初めて日本語を学んだ4年生が、私が教えた日本語を使って、訪問してくれた私の日本人の友人に自己紹介をしているのを隣で見ていた時とても感動しました。私が「自己紹介してみて」と言ったわけではないのに、自発的にコミュニケーションを取ろうと一生懸命学んだ日本語を使って会話を楽しんでいる姿を見て、「コミュニケーションの楽しさを伝えられた」、「教えて良かった」と改めて感じさせてくれました。これからも日本語の学習を通じて、人とコミュニケーションをすることの楽しさを実感してくれたらないいなと願っています。
留学で得た学びや経験は?
私が活動していた小学校では英語教育が盛んで日常的に英語を使うことが決められているため、子どもたちや先生方は英語で話してくれました。低学年の子どもたちも私に英語でコミュニケーションを取ろうとしてくれるのですが、まだ英語に慣れておらず、うまく伝わらない時もありました。それでも「せんせい!聞いて!」「私はせんせいと喋りたいの!」と一生懸命私に話しかけてくれ、「伝えたい」気持ちが大切なのだと子どもたちに改めて教えてもらいました。言語を学ぶ上で勿論正しい文法や語彙は重要ですが、この気持ちも忘れず大切にしていきたいです。
留学での経験は、今後の就職・進路選択にどんな影響を与えると思いますか?
毎日子どもたちと直接関わってとても充実していて楽しかったことから、自分は子どもと関わるのが好きだということを改めて感じ、将来も子どもたちの教育に関わっていく仕事がしたいと強く考えるようになりました。また、今回は先生として子どもたちに直接教えましたが、次は子どもたちの教育をさらに大きな枠組みから支えたいと感じるようになりました。具体的には各国で「質の高い教育」を普及させていく活動に携わりたいと考えており、大学院に進学し専門性を高めるか、現場での経験をさらに積んでいくか、卒業後の進路選択をしている途中です。
特に成長したと感じられる点
多様性への理解
その理由
ネパールの主な宗教はヒンドゥー教と仏教です。今まで日本でずっと暮らしてきて宗教概念にあまり馴染みのない私にとって、宗教を重んじるネパールでの生活は新たな価値観をもたらしてくれ、多様性への理解へもつながったと思います。毎日のヒンドゥー教式のお祈りから、輪廻転生を信じている方々の埋葬の仕方、生贄を使用するお祭りの儀式など、最初は困惑することも多かったです。しかし、長期間現地の方と過ごしたりお話を聞いたりしていく中で、ネパールの価値観を少しずつ理解することができ、多様性とは何かについて深く考えるようになりました。
これから留学する人に向けたアドバイス・メッセージを!!
国際社会貢献活動は、他の留学プログラムとは全く異なります。留学というと語学留学が主流だと思いますが、この活動では現地の方々と一緒に過ごして、何か活動をしていく中で、感じること学ぶことが沢山あります。今でも子どもたちとの思い出を振り返り、「幸せな5か月だった」「この5か月本当に行って良かった」と何度も感じています。私のように子どもに関わる活動から、現地の大学生や大人の方と一緒に活動するものまで沢山あります。もしご興味があるなら、とにかく挑戦されることを私はおすすめします!
清永 航平
国際学部 3年生(参加時)
- 派遣プログラム
- 国際社会貢献活動
- 派遣先機関
- カンボジアのジャパンハートこども医療センター
- 派遣時期
- 2024年度春学期


なぜ留学しようと思ったのか?
弱い者に寄り添える人になりたい。国際協力を志した時からずっと掲げている目標で、大学在学中に途上国でのプログラムに挑戦したいと思っていました。国際協力の現場に携われる国際ボランティアに惹かれ、また日本トップのNGOが派遣先の一つにあり、「プロフェッショナル」な環境で経験を積みたいという気持ちからも国際ボランティアへの参加を決めました。
さらには、大学1年時のベトナムFWで教室では学べない、「生」の学びや現場主義の大切さを知り、5ヶ月間途上国でボランティアに従事することこそが自分を成長させると思ったのも参加の理由です。
留学を実現するまでに、どのような準備をしましたか?
国際ボランティアへの参加に向け、事前準備として推奨科目やボランティアゼミの履修といった学内での授業だけではなく、実際に派遣される組織のイベントへの参加、派遣される組織や派遣国について文献調査を自ら行いました。
また、派遣先が医療機関だったため、非医療資格者の自分に何ができるのか、特に病院で入院している子どもたちのケアとしてできることや、その協力してくださる団体を探すこと。
さらに、自己分析を通してどの部分を派遣先で活かせるのか、またどの部分を5ヶ月間で改善させるべきなのかを明確にした上で、5ヶ月間の目標を設定することも行いました。
どのような留学生活でしたか?
毎日のように自分の弱さと向き合っては、乗り越えてを繰り返して少しずつ成長をしていった留学生活。常に問題意識を持ち、「自分に何ができるか?」「自分の何が求められているか?」を考え、いつも最善の自分で取り組むことを意識し続けました。
また、物事の「結果」よりもその「過程」に焦点を当て、自分が携わった仕事にどれだけ愛情を注いできたかを意識し、特に子ども向けのイベントでは、子どもファーストで、子どもたちの主体性を活かせるようなイベントづくりを心がけました。
本当に、生活や業務の全てから常に学びを得続けた5ヶ月間でした。
1日もしくはプログラム全体ののスケジュールを教えてください。
派遣先での業務がある日は、朝7時に起床して病院に併設されている食堂で朝食をとった後、8時の始業ミーティングから業務を開始し、12時30分頃から1時間半昼食を含めた休憩をとり、病院の近くでカフェや昼寝など自由に過ごしました。その後終業のミーディングの17時まで仕事をし、ミーティング後は17時30分まで残りの業務をして1日の仕事が終わります。その後は夕食を取ったのちに、カフェで課題や自己研鑽の勉強などをしました。 休日には、日の出を見に登山をしたり、カフェ巡りをしたり、時には首都に行ってお買い物や旅行をするなど体調や時間に合わせていろんなことを行いました。
留学中で、印象的な出来事
2つの「ありがとう」、これが私の留学生活で印象に残っていることです。一つ目は、日本人医師からの「ありがとう」。インターンとして、イベントマネジメントを任せて頂いた際、日本人医師から「あなたに任せてよかった、ありがとう」と自分の努力が認められた瞬間で、今でも鮮明に記憶しています。
二つ目は、入院している患者さんやその家族からの「ありがとう」。小児病棟でお茶会や動物ショーの視聴会を実施して、子どもたちや家族の方が自分の目を見て、心から「ありがとう」と言ってくださっている姿を見て、イベントをやってよかったと感じました。
留学で得た学びや経験は?
「目の前の当たり前は当たり前じゃない」、これに尽きます。5ヶ月間のインターン、イベントの企画・運営、外部団体の方々からのご支援。何より、元気に生きていること、自分らしさを表現できること、自分の好きなことをたくさんできること。また、自分の挑戦を心から応援してくれた家族、派遣中に何度も相談に乗ってくれた同期の派遣生、いつも親身に寄り添って頂いた国際ボランティア教職員の皆様がいてくださったこと。
留学を通して、自分がいかに恵まれた環境でボランティア活動に参加できたのか、本当に多くの方に支えられていたおかげであったかを再認識しました。
留学での経験は、今後の就職・進路選択にどんな影響を与えると思いますか?
留学での経験を通して、たくさんの選択肢を持つきっかけになっただけではなく、将来のキャリアを考える上での最も重要な軸を構築することができました。実際に、途上国の医療機関で、たくさんの生と死を目の当たりにし、また医療を受けられない人々の現実に直面し、人を救うことこそが自分がやりたかったことなのだと再認識しました。
また、この留学に参加したからこそ、留学を終えてからも次のキャリアや目標に向かって勉強や実践を積めています。この留学が自分の人生を歩んでいく上での原動力となり、またキャリアを進んでいく上での自信にもなりました。
特に成長したと感じられる点
チャレンジ精神
その理由
途上国の中でも厳しい環境の中で、目の前で困っている人に対して自分に何ができるのかを考え、果敢にチャレンジしていくこと。失敗を恐れずに、自分を信じてどんな困難にも立ち向かっていくこと。このような姿勢が求め続けられた5ヶ月間であり、自分でもチャレンジ精神が身についたと実感しています。
また、単に困難な状況をしんどいと捉えるのではなく、「自分が成長できるチャンス」だとしてそのような困難に対して取り組んでいけるように5ヶ月間を通して慣れたことも、チャレンジ精神の成長の証拠だと思います。
これから留学する人に向けたアドバイス・メッセージを!!
留学を行く際はハードルが高く、たくさんの不安があると思います。私もそのうちの1人でした。その際は「心の声」を大切にしてください。心からの「やりたい!」が留学への一歩を後押ししてくれるだけではなく、留学中あなたを一番支えてくれることになるでしょう。 また、世界には「誰かが取り組むべき」問題が山積みです。それを解決する「誰か」になってみませんか? 1人でも多くの人がその「誰か」として、世界中の弱き者に寄り添える者として、世界へ挑戦する一歩を踏み出してくれることを心から願っています。
林田 菜々子
法学部 3年生(参加時)
- 派遣プログラム
- 国際社会貢献活動
- 派遣先機関
- モンゴル日本人材開発センター
- 派遣時期
- 2024年度春学期





なぜ留学しようと思ったのか?
1,2年時に短期で留学プログラムに参加したことをきっかけに、より長期的な留学プログラムに参加してみたいと思った。国際協力に興味があったため、それを学ぶことができるプログラムであり、大学や語学学校で言語や学問を学ぶのではなく、現地で専門的な知識を学び実践的な活動をすることができるところに魅力を感じた。
留学を実現するまでに、どのような準備をしましたか?
国際プログラム履修前に推奨されている授業を履修したり、副専攻として国連外交プログラムを履修し、国際社会に関する基礎的な知識を習得するように意識した。また、実際に1,2年時にフィールドワークに参加し、実際に国際的な現場を見ることで、経験値を得た。
どのような留学生活でしたか?
現地の人々と密着した生活だったため、良い部分もカルチャーショックの部分も頻繁にみる機会があった。また、時間を有意義に使う機会が多く、現地の細かいことを機にしない文化に触れていたため、日本で生活しているよりも幸福度が高かったように感じる。ものや環境、サービスなど足りないものが多かったため、あるものでどう解決するか、と自分で考えて実行する機会が多く、さまざまなスキルが付いた。
1日もしくはプログラム全体ののスケジュールを教えてください。
9時から業務が開始し、基本的に18時まで働いた。フレックス制だったため自分の生活に合わせて出勤時間を決めることができ、インターン生にも柔軟に対応していただいた。4つの部署を約1か月ごとにローテーションし、ビジネス人材教育や日本語教育、相互文化促進に関わる業務に携わった。
留学中で、印象的な出来事
現地の青年海外協力隊の方々と様々な場所を訪れ、モンゴルの歴史や文化に触れたこと。それを業務の一環としてYoutubeに投稿することができたことが最も印象に残っている。大学に通っているだけでは経験できなかった景色を見ることができたり、様々なバックグラウンドをもった人と関わることができ、将来の見通しについて考え直すきっかけにもなった。
留学で得た学びや経験は?
将来の目標を持ち、目標のために努力することは人生において大切なことであると思うが、それ以上に今目の前にある現実を受け入れて今を楽しむことも重要であると思った。先を見て生活していると今ある幸せや自分の周りにある環境のよさに気づくことができず、スルーしてしまうかもしれないなと思った。また業務や日々のせ活を通して自分の強みや弱みを客観的に知ることができた。
留学での経験は、今後の就職・進路選択にどんな影響を与えると思いますか?
どんな仕事が自分に向いているか、苦手かを知るきっかけになると思う。インターンという形で実際に働く方々と近い環境で業務を行うことで、自分がどのくらいの規模で仕事をしたいか、今後何を学びたいかを考えることができた。就職することが正しいわけではなくて、大学院に行ったり海外インターンに行ったり、ギャップイヤーで自分のやりたいことを追及したり、自分を軸に人生をつくることができるようになると感じた。
特に成長したと感じられる点
タフネス
その理由
派遣期間中にボイラーの点検で2週間シャワーから温水がでないことがあり、炊飯器に給水機のお湯を貯めて限られた水量の中で入浴したことをきっかけに、忍耐力や問題解決に粘り強く取り組む姿勢がついたと考える。他にも言語が通じない中で5か月間生活したことは、精神的に大きく成長と思う。
これから留学する人に向けたアドバイス・メッセージを!!
人生の夏休みといわれる大学生活の中で、自分で決めたことを自分の力で叶えるという経験ができることの一つに、留学があると思います。良くも悪くも国際社会を知ることができると思いますし、自分をより知るきっかけにもなると思います。
林 優花
総合政策学部 3年生(参加時)
- 派遣プログラム
- 国連ユースボランティア
- 派遣先機関
- ナミビアのUNFPA
- 派遣時期
- 2023年度秋学期



参加しようと思ったきっかけ
参加を決めた一番の理由は、やはり将来国連で働きたいと思っていたからです。このように思ったきっかけは、中国にいたころに男尊女卑の考えが根強く社会に浸透していたことを肌身で感じ、強いショックを受けたことです。この経験からなぜこのような性差別が存在するのかについて疑問を抱くようになりました。その後、エマ・ワトソンが国連で行ったジェンダー平等を呼びかけるスピーチを見てとても共感し、ジェンダー平等の実現のためには自分が行動を起こさなければ始まらないと感じ、国連のような国際的な舞台で活躍したいという志が芽生えました。
大学に入学後、開発援助に関する実務経験が豊富な先生方のもとで学んでいく中で、開発途上国に貢献したいという気持ちもさらに強まりました。しかし、理論や教科書から学ぶだけでは現地の状況を理解することは難しく、途上国での援助がどのように機能しているかを知るには自ら足を運ぶ必要があると感じました。この国連ユースボランティアプログラムでは学部生であっても国連職員と一緒に活動することができ、国際援助の舞台裏を垣間見る絶好の機会であると考え、参加を決めました。
現地滞在中の印象的な出来事
印象的だった出来事の一つは、国連の日(United Nations Day)におけるUNFPAブースの運営に携わったことです。10月24日に記念される国連の日は、1945年に国連憲章が発効したことを記念し、国連憲章の誕生を象徴しています。2023年の祝賀テーマは「SDGsを巡る旅」であり、ナミビアと国連の長年にわたる関係性を称えながら、各国連機関がSDGsに向けた協力の成果をブースで展示しました。着任して間もなく国連の日におけるUNFPAブースの設計と運営を任され、さっそくブースのデザインに取り組みしました。UNFPAのブースではSDG5の「ジェンダー平等を実現しよう」という目標に向けての展示であったため、具体的にはUNFPAがSDG5にどのように貢献しているのか、どのような成果を挙げることができたかに着目して6つのポスターとビデオを作成しました。
これは私が初めて主体的に関わった活動であり、思い入れが深かったです。当日はナミビアの政府高官、市民社会組織及び各国大使館職員が出席されていました。急遽、私は上司からUNFPAブースに来場する全参加者に向けて3分間の歓迎と活動紹介をするよう頼まれました。原稿を準備することはできなかったが、ブース設計時の初心を思い出して取り組み、成功裏に終えることが出来ました。イベント後、UN Resident Coordinator(国連常駐調整官)とUNFPAの代表からは、「紹介が分かりやすく、ポスターのデザインも迫力があり好きだ」と褒められ、とても嬉しかったです。
国連ユースボランティア特設サイト
「国連ユースボランティア」は、アジアの大学として初めて関西学院大学が国連ボランティア計画(UNV)との協定に基づき、学生を開発途上国の国連諸機関にボランティア派遣しているプログラムです。関西学院大学を基幹校とし、2024年3月現在国内3大学(明治大学、明治学院大学、立教大学)と連携して実施しています。



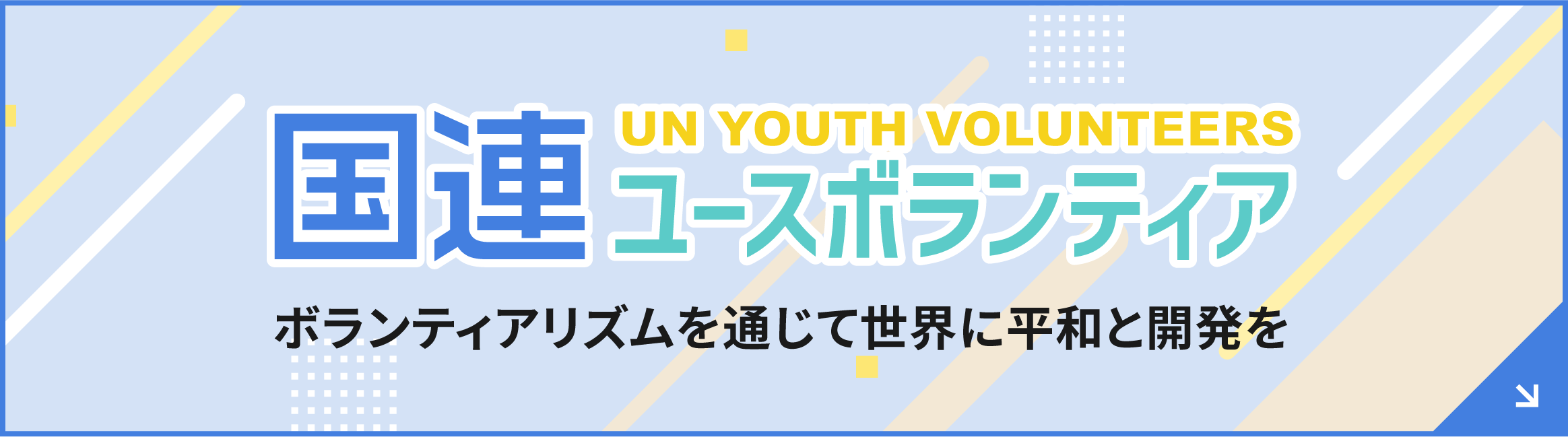
なぜ留学しようと思ったのか?
海外にルーツのある人が周囲に多く、高校生の時から留学に憧れを持っていたため、大学入学時から様々な留学プログラムを視野に入れて検討していました。総合政策学部の授業では途上国の課題や現状について学ぶ機会が多かったことと、友人の体験談を聞いて興味を持ち、途上国でボランティア活動を行う国際社会貢献活動に申し込みました。途上国で日本からの支援がどのように現地の人々に影響を与えているのかを、自分の目で見て学びたいと思いました。また、日本センターでは事業内容が多岐にわたるため、多様な経験ができると思いCJCCを選びました。
留学を実現するまでに、どのような準備をしましたか?
派遣前の必修科目である「国際ボランティアゼミ」で派遣国や派遣先機関について多角的に調べました。カンボジアの歴史・経済・残っている社会課題などを調べ、国全体の特徴を勉強しました。そして、CJCCの設立の経緯や事業内容を調べ、自分が担当する業務にはどのような目的があるのかを学びました。また元派遣生と連絡を取り、自分がやりたいと思っていることはどのくらい実現性があるのかをイメージしたり、家やお金などについて生活面での相談に乗っていただいていました。
留学中で、印象的な出来事
お互いに相手を理解しようとすることで、信頼関係を築けることを学びました。最初は、英語に自信がなかったことや、クメール語という現地語が理解できなかったことでコミュニケーションに苦労しました。ですが、英語では自分が伝えたいことが伝わっているかを繰り返し確認し、また職場に日本語学習者が多かったため、日本語で話しかけられた時に現地語で答えられるように現地語を勉強し日常的に使用していました。業務外でも職場の方とご飯を食べたり、祝祭日のイベントに参加したりなど、人と一緒に過ごす時間を大切にしていました。
1日もしくはプログラム全体ののスケジュールを教えてください。
文化や教育を通してカンボジアと日本の交流を促進する部署に配属されました。そこで、1つのイベントに向けて仕事をし、それが終わるとまた次のイベントの準備をするという流れで過ごしていました。滞在した10月から2月の間に主に4つのイベントがありました。10月には日本への留学を検討している現地の方向けの留学フェアがありました。12月にしめ縄を作るイベント、2月に節分文化を体験するイベントを開催しました。最後に2月中旬に毎年恒例の「絆フェスティバル」というカンボジアや日本の文化を楽しめるお祭りがありました。
留学での経験は、今後の就職・進路選択にどんな影響を与えると思いますか?
現場で途上国の発展に貢献したいという気持ちが強くなりました。漠然と国際協力に携わってみたいという気持ちは派遣前から持っていましたが、自分に本当に実現できるか分からないとどこかで思っていました。ですが、多様な課題が複雑に絡み合う現場を見て、現地の人々と一緒に現状を改善していける人になりたいと強く思いました。また、実際にカンボジアで働かれている日本人の方を見たり、お話を聞いていると、自分のキャリアのイメージが少し明確にできるようになりました。それから、様々なバックグラウンドを持つ人と文化や言語を学びながら一緒に働くことがとても楽しかったです。
特に成長したと感じられる点
主体性
その理由
過去にも派遣生が多かった機関だったため、職場の方々は学生の受け入れになれている雰囲気で、責任感のある仕事を任せていただく機会もありました。また、自分の考えを共有するとしっかりとフィードバックやより良いものを作るための提案などをいただける環境でした。そのため、自分のアイデアのクオリティや実現性にこだわり過ぎず、あまりまとまっていなくても周囲に相談してみることを意識していました。
これから留学する人に向けたアドバイス・メッセージを!!
語学力や金銭面や生活面など考えることがたくさんあり、参加することを悩んでいる方もいらっしゃると思います。ですが、特にこのプログラムは派遣前から派遣後まで、学校・先生・先輩・同期など制度においても精神的にもサポートしていただける体制が整っています。実際に派遣先へ行くのは自分1人ですが、たくさんの人に支えられて存分に自分の関心に挑戦できる機会になります。想像している何倍もの学びがあると思うので、少しでも興味がある方はぜひ参加をお勧めします!